居酒屋さんで「生ください!」と何度言ったことでしょう。「ビールください」じゃなくて、「生ください」。これ、重要ですよね。今回はそんな生ビールについてのお話をします。
生ビールってどんなビール?
さて、みなさんが想像する生ビールとはどんなビールでしょうか?お店でビールサーバーから注がれるあのビールこそ生ビール!そう認識されている方は少なくないのではないでしょうか。かくいう筆者もその一員でした。
しかし日本で【生ビール】とは、「熱処理をしていないビール」と定められています。
普段みなさんがコンビニやスーパーなどで買うビール缶や瓶のどこかに、【生】の文字を見掛けたことはないでしょうか?そうです、それが生ビールの証なのです。ですから【生】の文字を掲げている銘柄のビールは、缶でも瓶でもそしてお店で飲むジョッキに注がれたビールでも中味は同じ。どれもが全て【生ビール】なのです。
熱処理ビールはたったの3種類!
日本大手メーカーが手掛けているビールのほとんどは生ビールです。反対に熱処理をしているビールは2025年3月現在「キリンクラシックラガー」と「サッポロラガービール」(通称「赤星」)、そして2024年に発売された「キリン 晴れ風」の3種類のみとなっています。
さて熱処理ビールがどんなものかと言うと、その名の通り熱処理を施したビールのことです。1960年頃までは生ビールは存在せず、すべて熱処理されていました。
ではなぜ熱処理をするのか?それはビールに含まれる雑菌やバクテリア、そして酵母を死活させるためです。
ビールの炭酸とアルコールは酵母の働きによって生成されるため、酵母は必要不可欠な存在です。しかし酵母は放っておくとずーっとビールの中で生き続け、「過発酵」の状態になってしまいビールの品質が安定しません。また熱処理することで菌の増殖を抑え、保存性を高めるという目的もありました。
余談ですが、ベルギーのビールなどにはそのまま酵母を生かし続け、瓶や缶の中で二次発酵、三次発酵させるものもあります。味わいに複雑さが増し、アルコール度数やコクが高まることによって濃厚で芳醇なビールになるのです。著者はベルギービールが大好き!
ルイ・パスツールの大発明
さてはて熱処理の話に戻ります。「熱処理」なんて言うと生の鶏肉をフライパンでジュージュー焼いて中まで火を通す、なんてイメージが湧くかもしれませんが、ビールの場合は缶や瓶に詰めた後に、アルコールが飛ばない60℃〜70℃程度のお湯のシャワーを数10分当てて完了です。このような低温での加熱殺菌法のことを【パストリゼーション】と呼び、フランスの細菌学者ルイ・パスツールが考案しました。
パスツールは1866年にワインに対しての低温殺菌法を発明し、10年後の1876年には「ビールに関する研究」を発表、ビールでも低温殺菌法が応用できるとしたのです。この低温殺菌法によって、ビールの保存期間や輸送範囲を大幅に広げることが可能となりました。ドイツの古いことわざで「ビールは醸造所の煙突が見えるところで飲め」というものがあります。これは「ビールは新鮮なほど美味しく、時間が経つと本来の味わいが損なわれていく」というもでしたが、このパスツールの発明により、製造場所に関わらずより広い範囲でビールが楽しめるようになったのです。
ちなみに低温殺菌法(パストリゼーション)にはいくつか種類かあり、前述のように容器ごと熱処理する方法をトンネル・パストリゼーション、容器に詰める前に熱処理する方法をフラッシュ・パストリゼーションといいます。
アサヒとサントリーの「生論争」
反して生ビールの場合は「ろ過」によってこの酵母や雑菌を取り除いています。
およそ60年前、サントリーはNASAが開発したミクロフィルターを利用してのビールのろ過に成功し、「純生」という生ビールを発売して大人気となります。日本の企業努力には本当に驚かれますが、60年前でさえそのような技術があったのですから現代に至っては言わずもがなですね。
ちなみにこの【生ビール】を巡り、過去に一悶着ありました。サントリーの「純生」が発売された翌年1968年、アサヒが「本生」という生ビールを発売したのですが、謳い文句は「生きた酵母が入ったビール」。サントリーの「純生」は、ミクロフィルターでろ過され酵母が取り除かれているので「生ビールではない」と主張したのです。これにサントリーはもちろん大反論。この【生論争】はなんと10年も続き、1979年にようやく、生ビールとは「熱処理していないビール」と定義されたのでした。
あえて熱処理する理由は?
ろ過技術が向上した現代、わざわざコストのかかるパストリゼーションしなくてもいいのでは?と思うかもしれません。しかしあえて熱を加えることにより、味に厚みが増し、独特の香味が生まれます。というのもビール内に残っている僅かな糖が、「熱によりカラメリゼされる」というわけなのです。ほんのりカラメル香がするビールなんてわくわくしませんか?そんな方はぜひサッポロラガービール、通称赤星を飲んでみてください。著者も大好きなビールのうちのひとつです。
本日のまとめ
- 日本大手メーカーのビールのほとんどが【生ビール】
- 生ビールとは、熱処理していないビールのこと
- ビールなどを低温で殺菌する方法をパストリゼーションという
- 赤星はうまい
ペアリング
サッポロラガービール
- スタイル ピルスナー
- アルコール度数 5.0%
- 適温 5〜8℃(冷蔵庫から出してすぐ常温のグラスに注いだくらい)
- 推奨 グラスタンブラー型
✕
鶏もも肉のパリパリ焼き
〜皮はほどよく焦がしましょう〜
サッポロラガービールのスタイルはピルスナーですので、爽快な喉越しとスッキリとした後味が特徴です。鶏もも肉のジューシーさ、そしてパリパリに焼いた皮の香ばしさが、カラメリゼされた赤星の香りが抜群にマッチするはずです!ぜひ試してみて下さい。
ではまた!
サッポロ黒ラベルと赤星の飲み比べはいかがですか?
生ビールと熱処理ビールの味の違いがわかるかも!
さらに大手メーカーで唯一の【ドルトムンダー】であるエビスビールもセットになっています♬
参考文献
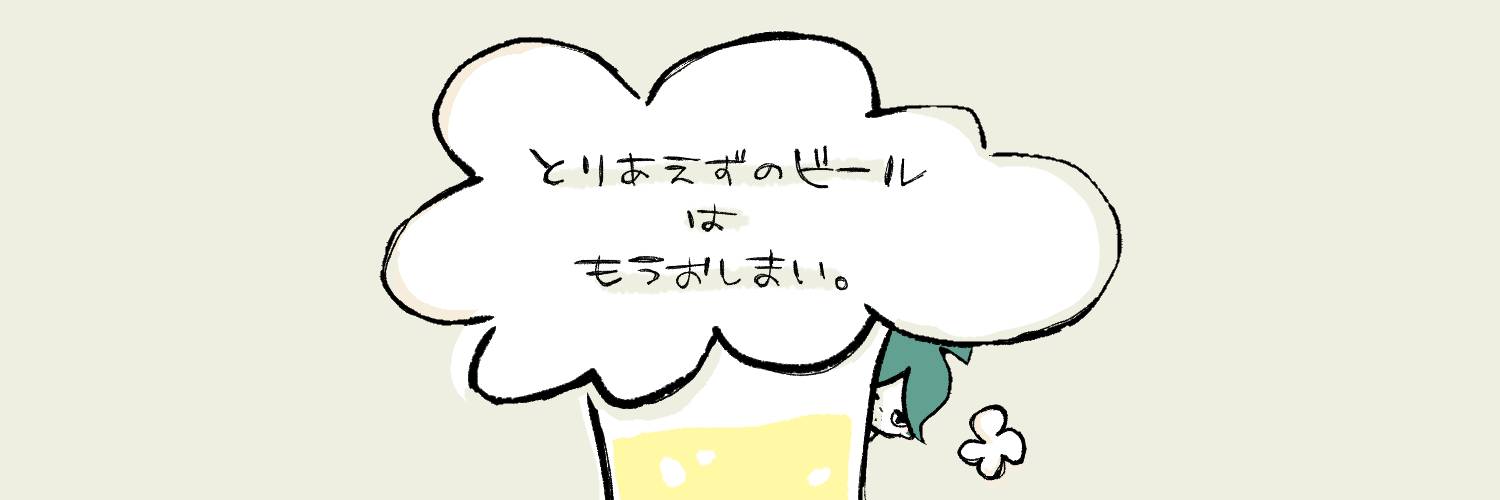








コメント