前回の【ピルスナー入門編】からお読みいただくと、より分かりやすいかと思います。
みなさんは普段どんなビールを飲まれていますか?最近は大手ビールメーカーが様々なスタイルのビールを打ち出していたり、クラフトビールなんかも以前よりずっと身近になりましたよね。
しかしそんな現代においても、まだまだ日本のビールの90%以上はピルスナーというスタイルのビールで占められています。ピルスナーの基礎は以前の記事で書きましたので、今回はもう少し踏み込んでピルスナーの歴史についてのお話をしようと思います。
ピルスナーの誕生
以前にも少し触れましたが、このピルスナーというスタイルはチェコ共和国のピルゼン(正式にはプルゼニ)という街で生まれました。このプルゼニはもともと伝統あるビール醸造の街でしたが、隣国ドイツのようにビール純粋令(ビールは麦芽、ホップ、水、酵母のみを原料としなさい、という法令)が敷かれておらず、19世紀の初期頃はビールの品質がかなり下がっていました。1838年にはそんなビールに嫌気が差した市民が暴徒化し、市庁舎の前で何十樽ものビールをひっくり返したなんて言われていますので、本当にひどい代物だったのでしょう。
そんなプルゼニのビールに危機感を持った街の有力者達が、お隣ドイツから醸造家であるヨゼフ・グロルを招きビール造りに協力してもらいました。
彼はミュンヘン出身でしたのでミュンヘン式のラガービールで醸造したところ、出来上がったのは黄金色に輝く透き通ったビール。当時のビールはほとんどが褐色だった上に濁っていましたので、これにはみな驚きを隠せませんでした。黄金色にきらきらと輝き、泡は密で雪のように白く、そして繊細なホップの香りに爽快な喉越し!そこにいた全ての人が一瞬にしてこのビールの虜になりました。
そしてこのビールは瞬く間にヨーロッパ全土に広がり、発祥地のピルゼン(プルゼニ)にちなんで【ピルスナー】と呼ばれるようになったのです。そして多くの類似品が生まれますが、プルゼニ側は「プルゼニ以外でピルスナーを醸造するな!」と訴訟を起こしました。裁判所はすでに【ピルスナー】が一般名詞化してるとして訴えを却下しましたが、プルゼニ以外の醸造家はPILSNERをPILESNERとしたり、PILSと簡略化する措置を講じたのでした。
水の硬度が要
ではなぜ、「ミュンヘン式」で醸造したはずなのにこんなにも違いが出たのでしょう?それはひとつにプルゼニの”水”にありました。他のヨーロッパ諸国が硬水であるのに対し、プルゼニは非常に柔らかな「軟水」。このプルゼニの軟水が、ピルスナーを造るのに適した水質であったのです。また使用した「ザーツ」というチェコ原産のホップとも相性がよく、さらにこの時に使用した淡色麦芽もピルスナーの色味に一役買ったのでした。
というのも当時の麦芽はほとんど濃色をしており、これは麦芽を焙燥(乾燥)させる際に薪や石炭を燃料にしていたため、煙の色が麦芽に移ってしまっていたのです。後にコークスという安価で綺麗に燃える燃料が開発され、淡色の麦芽が大量生産されるようになりました。グロルはこのように最新の燃料で作られた淡色麦芽を使用したのです。
余談ですが、水の硬度はそのビールのスタイルに大きく作用します。ミネラル量などの少ないなめらかな「軟水」は、前述の通りピルスナーのようなすっきりとした味わいのビールに適しています。反対にミネラル量などの多いしっかりとした「硬水」は、飲み口の重いエールビールやスタウト(黒ビール)に最適です。ちなみにそんなプルゼニの水の硬度は10ppm。日本は平均して48ppm、そしてイギリスのバートン・アポン・トレントは330mmp!この数値が高いほど硬度も高く、硬度が100mmpを大きく上回ると醸造出来るビールの数は数種類ほどになってしまうのだとか。なのでビールを醸造する際は、造りたいスタイルに合わせて水の硬度を調整するのが一般的です。(この作業を「水を磨く」といいます。)
色々なピルスナー
今や世界の70%以上のビールがこの【ピルスナー】だと言われていますが、ピルスナーにもいくつかのスタイル分けがあります。リストにしましたので参考にしてみて下さい。
ボヘミアンピルスナー(チェコ)
- 特徴 麦芽100%/琥珀色〜金色/モルトの甘味、コク/苦味は控えめ/チェコ産ザーツホップ由来のフローラルな香り
- 特記事項 元祖ピルスナー
- 代表銘柄 ピルスナーウルケル
ジャーマンピルスナー(ドイツ)
- 特徴 麦芽100%/淡い金色/すっきりクリスピー/苦味は強め/ドイツ産ハラタウ・ミッテルフリューホップ由来のフローラルでスパイシーな香り
- 特記事項 日本大手ビールのお手本
- 代表銘柄 ラーデベルガー
アメリカンスタイルピルスナー/アメリカンラガー(アメリカ)
- 特徴 淡い金色/強い清涼感、非常にドライ/苦味は控えめ/指定ホップはなし
- 特記事項 米やとうもろこしなど発酵を助成する副原料を25%以上使用する(つまり麦芽100%ビールではない)
- 代表銘柄 バドワイザー
少しだけホップの話
ボヘミアンピルスナーやジャーマンピルスナーを説明するときに欠かせないのが「ノーブルホップ」です。
ビールにとってホップとは、香り付け、苦味付け、抗菌作用、泡立ちを良くするなど、なくてはならない存在です。そんなホップですが現在200以上の種類があり、醸造家達はその中から造りたいビールのイメージに合ったホップを選び出します。ホップは大きく3種類に分けることができ、それぞれ
- 【ファインアロマホップ】香りと苦味が穏やかで上品
- 【アロマホップ】華やかな香り・香り付け用
- 【ビターホップ】苦味付け用
となります。そして前記の「ノーブルホップ」とは、ヨーロッパから古来使用されている伝統的な品種であり、特定の成分の基準を満たしているホップのみがノーブルホップとして認められています。現在は
- ザーツ(チェコ)
- ハラタウ・ミッテルフリュー(ドイツ)
- テトナング/テトナンガー(ドイツ)
- シュパルト/スパルタ(ドイツ)
の4種類のみであり、これらは全て【ファインアロマホップ】に分類されます。
ピルスナーにはこのファインアロマホップが使用されることが多く、日本のサントリー「プレミアムモルツ」にはザーツホップが使われています。先日久しぶりにプレモルを飲んだのですが、その香りの良さに思わずにんまりしてしまいました。どっしりとしたコクもあって、もしやボヘミアンピルスナーなんじゃないかと思っているのですが、どうなんでしょう。有識者の方、是非ご教授下さい。
ではまた!
ご紹介したチェコの「ピルスナーウルケル」とドイツ「ラーデベルガー」が入った世界のビール飲み比べセット!ぜひそれぞれのピルスナーの味の違いをお楽しみください♬
参考文献
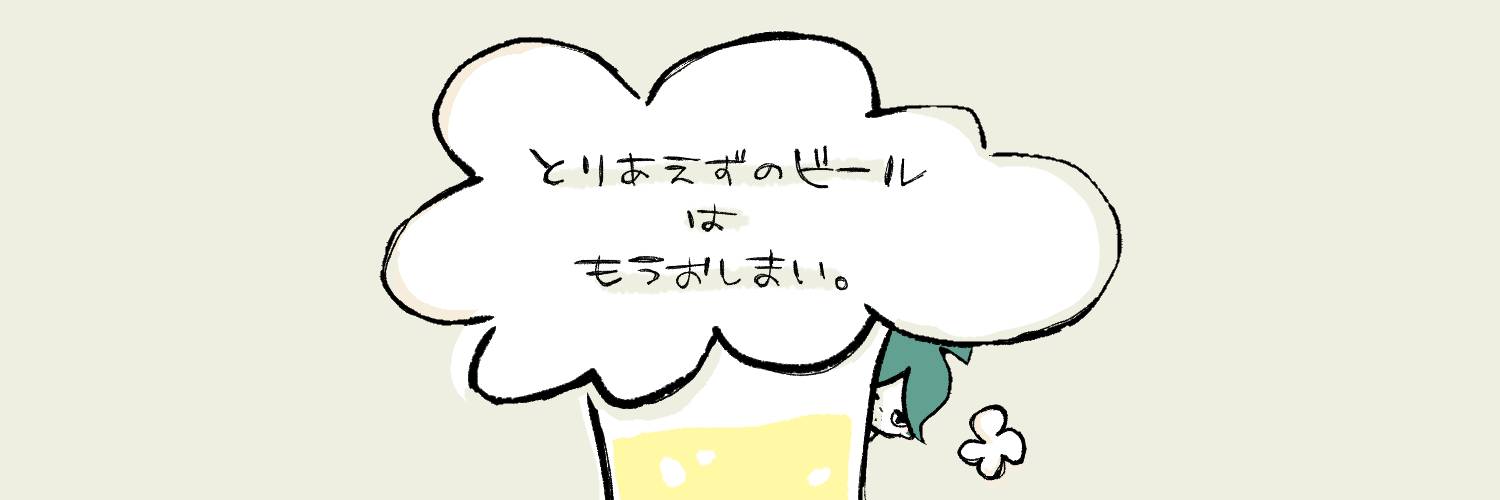
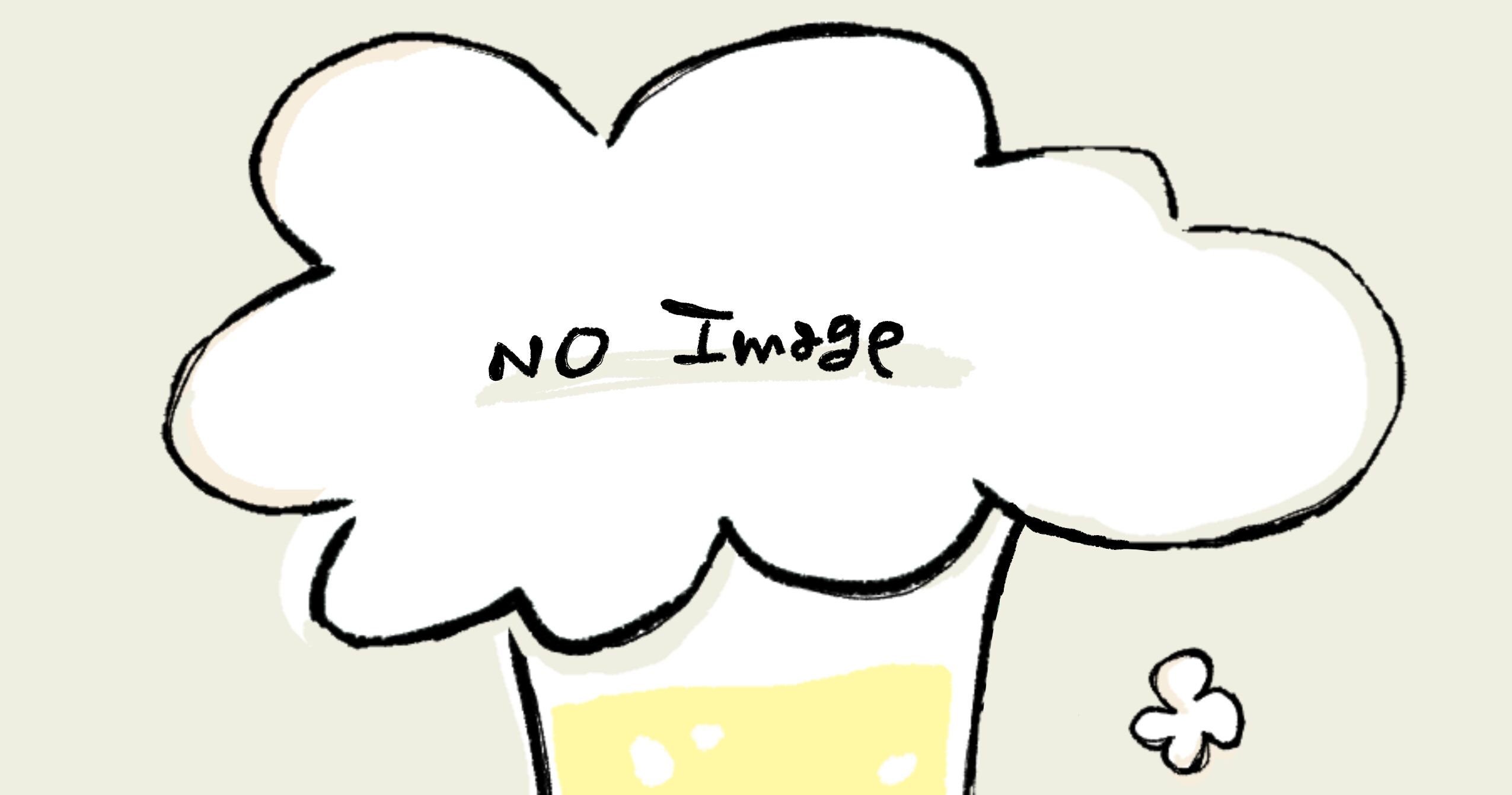



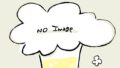

コメント