著者は20代の頃からビールが大好きで、特に飲み屋さんで飲む生中、いわゆる”生ビールの中ジョッキ”は格別だと思っていました。幸運にも無類のビール好きの友人がいたおかげで、調子の良い日なんかは2人で20杯以上の生中を飲み、2軒目でもまた生中をたらふく飲むというなかなかワンダフルな青春時代を送ることが出来たように思います。(今思えば村上春樹著の「風の歌を聴け」のような話ですね。寝ても覚めてもビールを飲みまくってる素敵な青春小説です。ご興味あれば是非!)
生中が美味しくなる条件
そもそもなぜ飲み屋さんの生中はこんなにも美味しく飲めるのか?前回の記事ではビールサーバーが作り出すクリーミーな泡の存在にフォーカスしましたが、それ以外にもお店の雰囲気や料理、気の合う友人、はたまたビールサーバーの管理が行き届いている(サーバーのメンテナンスの有無はビールの味に大きく作用します。)など、たくさんの条件が合わさったとき最高のポテンシャルを発揮するのが”生中”だと思っています。
ビールジョッキの歴史と特徴
そんな生中の醍醐味は、なんと言っても「ビールジョッキ」。日本におけるビールジョッキの歴史は深く、明治時代後期(1900年のはじめあたり)のビアホールではすでにジョッキによってビールが提供されていたそう。しかも500〜1000mlの容量があったのだとか!(現在のジョッキは350〜500mlが一般的です。)ビールの聖地ドイツでも、オクトーバーフェストというビールの祭典で”マス”と呼ばれる1000mlのグラスで何杯ものビールを飲むそうですが、それに匹敵するサイズです。
そんなビールジョッキの特徴といえば、やはりその形状にあります。ガツンと乾杯しても割れる心配のない厚めのガラス、持つとずっしりとした重みを感じられる特別感、そして持ち手があることによってビールに熱が伝わりにくく、その厚さも相まって長い時間ビールを美味しく楽しめるのです。
ジョッキと泡の関係
それでは自宅でビールを楽しむのもやはりジョッキが一番なのでしょうか?…答えは”NO”だと筆者は考えています。前述した通りジョッキで飲むビールの良さは、飲む際の環境的要因が大きく関わってくるからです。更にビールサーバーの存在が非常に大きく、サーバーで作った泡のスムースさはジョッキの厚い飲み口と相性が良いのですが、残念ながらこの泡を自宅で作るのは難しいのです。詳しくはこちら。
なぜジョッキとサーバーによる泡の相性が良いのかというと、それはビールを飲むときの我々の口の大きさにあります。ちょっと想像していただきたいのですが、ジョッキでビールを飲むときって口に力は入れないですよね?その口に力を入れずに唇を軽く開いたときの幅こそ、理想的なビールジョッキの厚みとされているのです。そこで大事になってくるのが泡の質感で、ビールサーバーで作られたスムースな泡はビールと共に唇の僅かな隙間からするすると滑り込んでくれますが、自宅でジョッキに注いだビールではそうはいきません。泡だけ渋滞を起こし、グラスに取り残されてしまいます。泡なしの生中でしたら問題ないかもしれませんがやはり泡あってこその生中ですよね。
なので著者は、ジョッキの気分なら飲み屋さんで、自宅で飲むなら相応のグラスで、ということをオススメします。
ビアスタイルに合わせてグラスを変える
それでは相応のグラスとは一体どんなものでしょうか?ようやく本題に入ります。ビールをより美味しくいただく際の条件として「口当たりの良さ」が挙げられます。これは特にグラスの”薄さ”に左右され、繊細で薄いグラスの方が飲む際にグラスの存在を感じにくいため口当たりが良く、ビールの味をダイレクトに感じられると言われています。これはワイングラスが繊細に作られているのと同じ理由です。しかし薄ければなんでも良いというわけではありません。ビールにはたくさんの種類、味わいがあり(ビアスタイルといいます。)、そのビアスタイルの特徴や良さを最大限に引き出せるような形状のグラスで飲むことが、ビールに対する礼儀でもあるのです。(と筆者は思っています。)
おいおい待ってくれよ、そのスタイルってやつは一体いくつあるんだ?と思った方、驚いてください、現在世界には150種類以上のビアスタイルがあるのです!また銘柄によっては専用のビールグラスを製造しているところもあり、特にベルギーではほとんどのビールに専用のグラスがあるのだとか。そして飲み屋さんで飲みたい銘柄のビールのグラスが全て出払っていたら、グラスが戻ってくるまで飲ませてくれないという徹底っぷり。いかにグラスを重要視しているかが伺えます。
結局のところグラスは2種類あればいい
ともあれ現実的に、そんなにたくさんのグラスを所持するのは難しいですよね。かくいう筆者もいくつかのビールグラスを持っていますが、メインで使っているグラスはたった2種類。そう、最低限2種類のグラスがあれば豊富なビアスタイルにも対応出来るのです!なんだかハードルが一気に下がった気がしませんか?しかもどちらもDAISO(ダイソー)で手に入れることが出来ますので、そちらも併せてご紹介します。
さてでは実際にどんなグラスを用意すればいいかというと、「タンブラーのような飲み口が広がっている円筒型」と「ワイングラスのような飲み口がすぼまっているチューリップ型」の2種類になります。
円筒型のグラスには、香りは穏やかでスッキリとした喉越しやドライな味わいが特徴の【ラガータイプ】のビールがぴったりです。アサヒスーパードライやキリン一番搾りなど、「日本でよく見かけるビール」は概ねこのグラスでOKということになります。なぜラガービールには円筒型のグラスが適しているかというと、口に流れ込んでくるビールの量にあります。このタイプのグラスは飲み口が広くなっているため、少し傾けただけでもたくさんの量のビールが口の中に入ります。これはラガービールのようなぐびっと爽快感を味わうビールと相性が良いのです。また飲むときの”舌の位置”も関係していて、ジョッキなど口の広いグラスでビールをいただくとき、舌先は自然とグラスの縁に触れますよね。すると流れ込んでくるビールが一番先に到達するのは舌先であり、この舌先には甘味を感じる感覚組織が集中しているため「麦芽の甘味」を、そして次にビールが到達する舌の奥には苦味に敏感な組織があるため「ホップの苦味」を感じます。このふたつの味わいがほどよく中和したのち、苦味に一番敏感な舌の付け根を通過することにより甘味が消え、最後にはドライなフィニッシュになるのです。人間の身体って面白いですねえ。
対してワイングラスやチューリップ型のグラスには、香りが豊かでコクがあり、喉越しは控えめな【エールタイプ】のビールがぴったりです。芳醇な香りをグラスの膨らみに籠もらせることによって、その香りをより堪能することができるのです。【エールタイプ】というとあまり馴染みがないかもしれませんが、スーパーやコンビニでよく見かける「よなよなエール」もそのうちのひとつ。このよなよなエールはヤッホーブルーイングという長野県の軽井沢に本社を構えるブルワリー(ビール醸造所)で醸造され、他にも様々な種類のエールビールを販売しています。「水曜日のネコ」や「インドの青鬼」というビールも看板商品のひとつかと思いますが、見かけたことはあるでしょうか?
さておき、チューリップ型のグラスは飲むときの口の形がおちょぼ口のような、唇が少し前へ出る形になります。これは飲み口の広いグラスに比べて流れ込んでくる液体の量が少ないために「液体をはやく取り込もう」とする行動だそうです。この行動のおかげでエールビール特有の香りやコクをゆっくりと堪能することが出来るのです。ちなみにこのようなグラスで飲み物をいただくとき、舌は口の奥で丸まっていますので一番最初に感じる味覚は甘味ではなく、舌の両脇にある感覚組織が敏感な「酸味」だそうですよ。
オススメビールグラス2選
みなさんどうでしょうか、グラスで飲んでみたくなってきましたか?
そんな方はご自宅に良さげなグラスがあれば是非そちらを使ってみてください。ちょうどいいグラスがないよーという方は、まずはDAISOの「ビールグラス300ml (JANコード4550480267944)」と「赤ワイングラス270ml(JANコード4984343635753)」から始めてみてはいかがでしょうか。110〜220円で購入可能です。グラスへの注ぎ方については過去の記事を参考にしてみてくださいね。みなさんのビールライフが、より良いものになればいいなと思います。
ではまた!
本日のまとめ
- ジョッキでビールを飲むなら飲み屋さんでいただきましょう
- 自宅で飲むなら相応のグラスで
- ラガービールならタンブラーのような円筒型
- エールビールならワイングラスのようなチューリップ型
本日のペアリング
インドの青鬼(ヤッホーブルーイング)
- スタイル アメリカンIPA
- アルコール度数 7.0%
- IBU(国際苦味単位) 60
- 使用ホップ アメリカ産ホップ(品種までは明記なし)
- 適温 9℃(公式より)
- 推奨グラス チューリップ型
✕
ビーフステーキ ガーリックチップトッピング
IPAとは【インディアペールエール】の略記です。イギリスが発祥で、ホップの香りや苦味が一般的なビールと比べるとかなり強いビールです。アルコール度数もやや高めの7.0%前後。いまや世界で(特にアメリカで)最も人気のあるスタイルと言っても過言ではなく、多くの人に飲まれています。
IPAは同じくイギリス発祥のペールエールの強化版、と考えていただければ差し支えないかと思いますが、ではなぜ「インディア」なのでしょうか?
1800年代インドがイギリスの植民地だった時代、イギリス人が大好きなペールエールをインドまで運びたい!ということから始まります。しかしイギリスからインドまでの航海は赤道を二度通る必要があり、航海途中にビールがどうしても腐敗してしまうという問題がありました。そこで殺菌効果のあるホップを大量にビールに入れてみた結果、品質が長持ちするし味わいもパンチが効いていて美味しいじゃん!…ということで、新しいスタイルの誕生です。つまりインドまで運ぶために作ったペールエールだから【インディアペールエール】なのです。
インドの青鬼はアメリカンIPAというスタイルのIPAで、アメリカンIPAは主にアメリカ産のホップが使用されています。本家のイギリス産ホップを使ったものはイングリッシュIPAと呼びますが、イギリス産のホップは花や草の香りがするものが多いのに対し、アメリカ産のホップは柑橘やパッションフルーツの香りが特徴です。
そんなインドの青鬼は、深いコク、弾けるようなグレープフルーツの香り、そして圧倒的なホップの苦味に初めて飲む方は思わず目を見開くはずです!そんなパンチの効いたビールには、パンチのある料理でペアリングするのがハナマルです。そしてアメリカ産ホップ特有の爽やかな柑橘の香りが、ステーキの油をすっきり流してくれますよ。是非ガツンと一発、食らってみてください。
ガツンと一発食らいませんか?「インドの青鬼」をはじめ、ヤッホーブルーイングの定番商品が勢ぞろい!ペールエール、セゾン、ホワイトビールといった様々なスタイルのビールが詰まったセットです。
参考文献
電子版
こっそりオススメしておきます…私のバイブル。
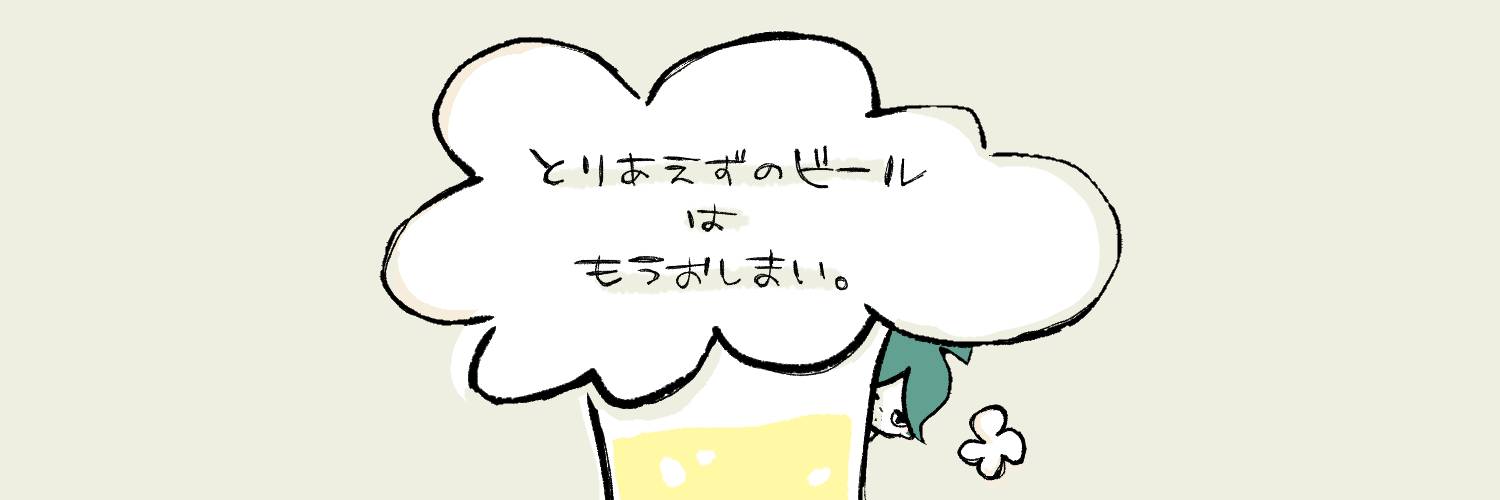
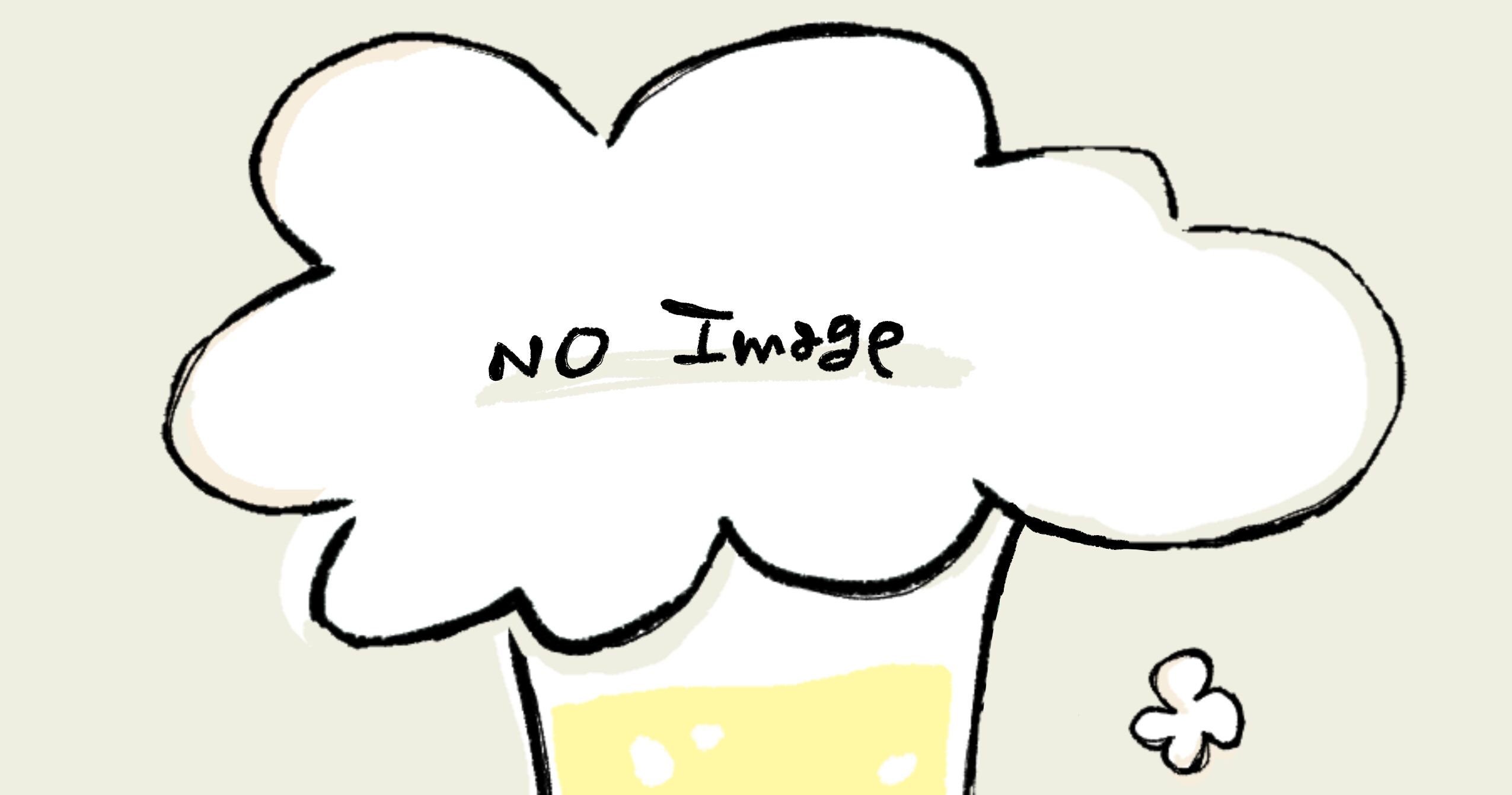








コメント