飲み屋さんでいただく生ビールって本当に美味しいですよねえ。家で飲むのとは全然違う!と感じる方もいらっしゃるかと思いますが、飲み屋さんのビールサーバーから出てくるビールと、スーパーなどに売っているビールは銘柄が同じであれば中味も同じだということをご存知ですか?この事実を知った時、筆者は「そんなバカな!」と頭を抱えたものですが、何故こんなにも味が違うように感じるのか?そして自宅でもお店のように美味しくいただくにはどうしたら良いのか?今回はそのあたりのお話をします。
ビールサーバーの泡はすごい
飲み屋さんと自宅との大きな違いにビールサーバーの存在があります。このビールサーバーというのは本当に凄い代物で、まずサーバーのハンドルをクイッと引くと、常温のビールが入った樽(「ケグ」といいます。)に圧力がかかります。するとビールがホースを通ってサーバーへと押し出され、サーバー内で一瞬にして冷却されて注ぎ口(「タップ」といいます。)から出てくるのです。また泡出し機能が備わったサーバーもあり、これはハンドルを押し込むことできめ細かい泡がタップから出てくるというものです。このクリーミーでスムースな泡はサーバーならではの質感だと思います。
(最近ではアサヒから「生ジョッキ缶」という缶ビールが発売されましたね。開けるとじゅわ〜っと上がってくるあの泡は、まさしくサーバーから出る泡のような質感!企業努力って凄いです。)
では、このクリーミーな泡を自宅で再現出来るかというとなかなか難しいと思います。というのも、ビールサーバーの泡は超音波による細かな振動をビールに与えて作り出しているからです。最近は自宅でもサーバーのような泡を作ることが出来るハンディビールサーバーも販売されていますが、それだけ日本ではビールの泡が重要視されていることが分かります。
そんなビールの泡にはどんな役割があるかというと、泡でビールを蓋することにより炭酸ガスが抜けるのを防いだり、空気に触れることによる酸化防止。そしてなによりクリーミーでスムースな泡は口当たりを良くしてくれ、さらに口の中に流れ込んでくるビールと泡の量を調節してくれるのです。
え〜でも家では特別な機械がないとクリーミーな泡は作れないんでしょ?とお思いの方、確かにビールサーバーのような泡を作るのは難しいですが、特別な機械を使わずとも家ならではの泡の作り方があります!今回はアサヒスーパードライをモデルにして、美味しい泡の作り方(注ぎ方)をご紹介します。
①ビールに合ったグラスを用意する
やっぱグラスに注がないとダメ?面倒だよ〜という方は、「アサヒ生ジョッキ缶」を飲みましょう。美味しいですよね、生ジョッキ缶。いやしかしそれでも、読んでいくうちにきっとグラスに注ぎたくなる、はず……。
さてアサヒスーパードライはピルスナーというスタイルのビールで、このピルスナーにはタンブラーのような細長い形のグラスが相性が良いです。オススメはダイソーのビールグラス。100円だし薄く設計されているので口当たりがよく、また薄いことでグラスからの温度の影響を受けにくいですよ。
②グラスを一度水でゆすぐか、氷水にくぐらせる
氷水でグラスを冷やすことで格段に美味しくなりますが、いやぁちょっとそこまでは…という方は水でゆすぐだけでOKです。ゆすぐ理由はグラスに付着している埃を洗い流すため。埃が付いているとビールの泡立ちが極端に悪くなります。同じ理由で水でゆすいだあとはふきんなどで拭いたりはせず(繊維が付着してしまうため。)水切り程度で構いません。水で濡れることにより、グラス内の目には見えない凹凸が水分で覆われてスムーズにビールを注ぐことが出来るのです。
③グラスにビールを注ぐ
注ぎ方にもいくつか種類がありますが、まずは日本大手ビールメーカーが推奨している「三度注ぎ」をご紹介します。
1、グラスをテーブルに置いて、出来るだけ高い位置からグラスの底を目掛けてビールを注ぐ。グラスが泡で一杯になったら、注ぐのをやめて泡が落ち着くまで小休憩。2〜3分かかります。
2、泡とビールの比率が1:1になったならば、今度は低い位置から泡の下に滑り込ませるようにゆっくりとビールを注ぎ込む。泡がグラスのフチから1センチほど盛り上がったら注ぐのをやめてまた小休憩。
3、泡が落ち着いてきたら、最後に泡の中心から残りのビールをすべて注ぐ。理想的な泡とビールの比率は3:7。このとき泡がグラスのフチから2センチほど盛り上がっていたらエクセレントです!
④いただきます
グラスに注いだことでわくわく感が数段アップしたような気がしませんか?実は、人間の五感の情報収集力は視覚が80%、味覚が1%なんて言われています。いわゆる”映え”が重要視されているのですね。しかしビールはグラスに注げば美味しくなる上に映えるってんだから、なんてすばらしい飲み物なんでしょう!缶のまま飲むのと比べていかがでしょうか?もしもう1本同じビールがありましたら実際に飲み比べてみるのも面白いと思います。(ちなみに缶のままビールを飲むと、炭酸がダイレクトに身体に入るのでゲップが出やすいそうですよ。)
三度注ぎのいいところ
さて三度注ぎをするメリットとして、ビールの炭酸がほどよく飛んで旨味を感じやすくなることが挙げられます。また三度注ぎで作られた泡は、ビールサーバーのものとはまた違った質感ですがフワフワのモコモコまるで雲のよう!思わずにんまりしてしまいます。さらにそんなモコモコの泡がビールの苦味成分を吸収し、飲み始めは苦味が少なく、飲み進めていくうちにそんな苦味成分を吸収した泡がビールと混ざり合ってビールに苦味が増していくという味の変化を楽しむことが出来るのです。
ちなみに「一度注ぎ」や「二度注ぎ」といった注ぎ方もあります。簡単にまとめましたので、気分に合わせて変えてみてはいかがでしょうか?
一度注ぎ
✷炭酸の爽快感が堪らない。カァーッといきたいときはこれ!(筆者は一度注ぎが一番好きです。)
<注ぎ方>
1、グラスを傾けて持ち、低い位置からグラスの真ん中あたりを目掛けて注ぐ。
2、グラスの7割方注いだらグラスを徐々に立てていきフィニッシュ!
二度注ぎ
✷一度注ぎと三度注ぎの良いとこ取り!やや強めの炭酸と、フワフワの泡が良いバランス。
<注ぎ方>
1、グラスをテーブルに置き、グラスより少し高い位置からビールを勢い良く注ぐ。目安はグラス8分目くらいまで。
2、ビールと泡の比率が1:1になったら、先程よりも低い位置から泡の下にビールを滑り込ませるようにゆっくり注ぐ。泡が落ち着いたらフィニッシュ!
泡の適量は?
日本では泡とビールの比率は3:7が黄金比とされていますが海外では必ずしもそうではありません。例えばアメリカでは出来るだけ泡の量を少なくするのが一般的で、これはビールの液体部分がグラスの容量パンパン入ってた方がいっぱい飲めるよね、的な考えだそう。
反対にチェコでは「ミルコ」という泡が9割、ビール1割という飲み方もあります。そんなビールが出てきたら日本では非難轟々でしょうが、チェコの「ピルスナーウルケル」という銘柄の伝統的な飲み方だそうです。いつか飲んでみたいものですね。
ちなみにかつて日本では、このビールの泡の量を巡って裁判が起こりました。舞台は1940年の上野広小路のビアホール。お客さんが出されたビールに対して「ほとんどが泡じゃないか!こんなのビールじゃない!」とクレームを入れたことから始まります。騒ぎを聞きつけた警察が帳簿を確認すると、たしかにビールの仕入れ量と売上量が合わない。そして取り調べの結果、公定価格違反として起訴されてしまったのです。
この裁判の争点は、「ビールの泡はビールか否か」でした。ビアホール側はもちろん泡もビールだと主張。そして鑑定の結果、ビールの泡はビールであるということが証明されたのです。ビアホール側の勝利で幕を閉じました。…いやぁたしかに泡がビールじゃなかったら一体なんなんだって感じですが、それでもやっぱり泡だらけのビールが出てきたら著者はちょっと悲しい…かも。

だいぶ話が脱線してしまいましたが、ビールのスタイルによっても泡の適量は変わってきます。ピルスナーなどの喉越しが特徴のビールは先の三度注ぎのような注ぎ方、泡の量で問題ないかと思いますが、苦味が特徴のペールエールやIPA(インディアペールエールの略記です。IPAはペールエールの強化版みたいなスタイルです。)は、泡立てると苦味成分が泡に吸収されひと口目の苦味に口内が支配されてしまい、ビール本来の味が感じにくくなってしまうため優しく注ぐことが推奨されています。
このように、国やスタイルよって泡の扱い方は様々です。好みの問題もありますし、(実際筆者は泡少なめが好きです。)泡とビールは3:7!という概念は一旦隅に置いておき、自分が一番好きな飲み方を見つけてみてはいかがでしょうか?
本日のまとめ
- 自宅でビールを楽しむ際は、出来るだけグラスに注ぐ
- グラスの形状はビアスタイルに合ったものを(詳しくは次回のグラス編で)
- 注ぐ前に水(または氷水)でゆすぐ
- 日本大手ビールメーカーは【三度注ぎ】推し
- 他にも【一度注ぎ】や【二度注ぎ】などがある
- 必ずしも泡とビールの比率は3:7が正解とは限らない
本日のペアリング
ピルスナーウルケル
原産国 チェコ
スタイル ボヘミアンピルスナー
アルコール度数 4.4%
適温5〜7℃
✕
ポトフ
ピルスナーウルケルはチェコのピルゼンで1842年に誕生した、ボヘミアンピルスナーというスタイルのビールです。いまや全世界で愛され飲まれているピルスナービールですが、実はそんなピルスナーの元祖がこのピルスナーウルケルなのです!かつてのビールはほとんどが褐色をしていて、ピルスナーのような黄金色に輝くビールは存在していませんでした。そんな中、ピルゼンの地で初めて醸造法がもたらされ、隣国ドイツの醸造家を招いていざビールを造ってみたら出来上がったのはなぜか黄金色のビール。これはピルゼンの”水”がヨーロッパ諸国には珍しく軟水であったことが関係していました。そしてこの黄金色のビールは、ピルゼンの地名にちなんで「ピルスナー」と名付けられ、瞬く間に世界で大人気となるのです。そんなピルスナーウルケルの伝統的な飲み方は、先に紹介した「ミルコ」の他に、「ハラディンカ」というものがあります。こちらが最もポピュラーで、注ぎ方は二度注ぎに似ています。異なる点は、「泡を作ったあと泡の中心からビールを注ぐこと」そして「泡の量は必ず3フィンガー(指3本分)」というところです。ご自宅でも是非挑戦してみて下さい。
そんなチェコには「ブランボラチカ」というじゃがいもなどが入った伝統的なスープ料理があり、これは現地のビアホールのメニューにも載っているそう!ポトフよりややとろみがあって、バターなども入っているみたいです。もしポトフではなくブランボラチカに挑戦してみたい!という方は日本チェコ友好協会のサイトを掲載しますので参考にしてみて下さいね。
ビールで世界旅行してみませんか?ご紹介したチェコのピルスナーウルケルはもちろん、デンマークやインドネシアなど計6カ国のビールが詰まった飲み比べセットです!
参考文献
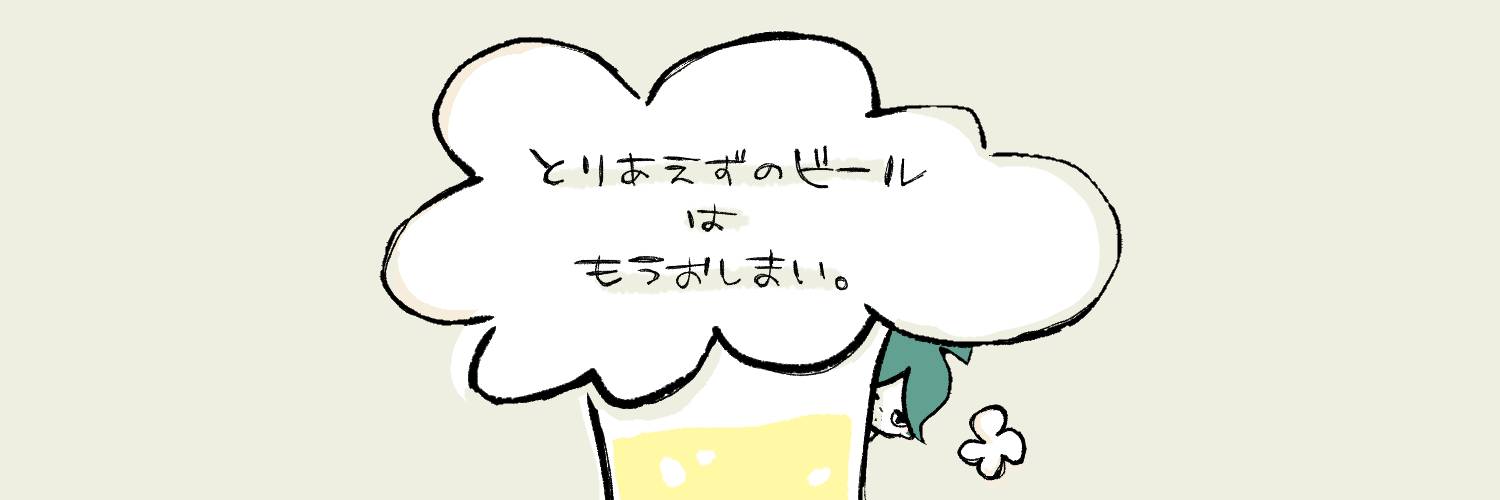






コメント