最近よく耳にする「クラフトビール」。みなさんはどんな印象がありますか?「普通のビールとは違った味」とか「なんだかオシャレよね」など様々だと思いますが、近頃はブルワリー(醸造所)やクラフトビールが飲めるお店なんかも増えてきて我が国日本でもムーブメントが起こっていることが伺えます。
クラフトビールの起源はアメリカとされていますが、いまや日本をはじめとするアジア諸国のみならず、ドイツやイギリスといったビール伝統国はもちろん、「ワイン国」であるフランスやイタリアにまでムーブメントが巻き起こっています。つまり世界的に見てもクラフトビールは流行の真っ只中!嬉しいことこの上なしですね。
そんな人気沸騰中のクラフトビールですが、では「クラフトビールって何?」と聞かれたときどのように説明しますか?
日本ではよく「小規模のブルワリー(醸造所)で造られていて〜」などと紹介されることが多いですが、その由縁はどこから来ているのでしょうか。今回はそのようなクラフトビールの定義についてのお話です。
禁酒法を経てのクラフトビール
定義の話をする前に、ざっくりとクラフトビールの起源についてお話しします。
前述の通りクラフトビールはアメリカで生まれました。その昔1920年、アメリカで禁酒法が発令され、アメリカ全土にあった小規模ブルワリーは廃業を余儀なくされました。この禁酒法は1933年に廃止されますが(13年間もお酒飲めないの?!と思った方、この禁酒法は販売を禁止するものであって、飲酒を禁止するものではありませんので安心して下さい。結果闇市などで粗悪なお酒が出回って人々をアルコール中毒にしてしまったのですが。)、その後小規模ブルワリーの数はなかなか回復せず、大手のビールメーカーが市場を独占していきます。
そんな大手メーカーが造るビールは米やとうもろこしを大量に使用した、非常にライトな味わいの【アメリカンピルスナー】でした。そんな市場が30年ほど続き、ついに1968年、【カリフォルニア・コモン】という伝統的なビールを再現し販売する会社が頭角を現したのです。大手メーカーの画一的なビールに飽き飽きしていた”ビール愛好家”達は両手を挙げ喜び、さらに1978年に酒類の自家醸造(ホームブルーイング)が解禁されると、そんな愛好家達は大手ビールのアンチテーゼとでも言わんばかりにこぞって世界の伝統的なビールや自分が飲んでみたい、美味しいと思えるオリジナルのビールを造るようになりました。そうです、これがクラフトビールの始まりであり、クラフトビールの真髄なのです!
なにをもってクラフトビールとするか?
ではここからは実際に、クラフトビールの定義について見ていきましょう。
パイオニアであるアメリカは、「クラフトビール」ではなく「クラフトブルワー(醸造者)」について定義していますが、それは以下のような3条項です。
①醸造所が小規模で、ブルワーの目の届く製造を行っている
②大量生産のビール(大手ビールメーカー)からは独立したビール造りを行っている
③酒税免許を持って実際に醸造している
この定義は2005年に定められましたが、当時は③の条項が現在と全く異なったものでした。それは「基幹商品が麦芽100%(オールモルト)か、出荷量の5割以上がオールモルトもしくは風味を強化する目的で他の原料を使用した製品」というもので、これは【アメリカンピルスナー】を排除するための条項でした。
そしてこの③は2014年には「オールモルトか、もしくは伝統的または革新的な原料と発酵に由来する風味のビール」と変更され、更に2018年には全て削除されて現在の条項となったのです。
日本でも2018年に全国地ビール醸造者協議会(JBA)によるクラフトビールの定義が発表されていて、内容は基本的に現在のアメリカのクラフトブルワーの定義を踏襲したものですが③だけが大きく異なります。以下全文引用です。
伝統的な製法で製造しているか、あるいは地域の特産品などを原料とした個性あふれるビールを製造している。そして地域に根付いている。
(⚠アメリカではクラフトブルワーについて定義していますが、日本ではクラフトビールを定義しています。)
さてそんな日本のクラフトビールですが、先にも述べたように最近では大手ビールメーカーもクラフトビール事業に乗り出しています。
キリンの「スプリングバレー」などがその代表格だと思いますが、この記事を読んでいる方はこう思ったでしょう。
「おいおい、キリンって大手じゃん!ってことはスプリングバレーはクラフトビールじゃないよね?」
このような大手参入が近年クラフトビールについての定義がフワフワしている一因でもあり、世間でも「つまりクラフトビールって一体なんなんだ!」という議論が続けられているのです。
そんな”大手”キリンスプリングバレーは、クラフトビールについて以下のように発信しています。以下全文引用です。
造り手たちの創造性が生む多様なおいしさで、人生の楽しみが広がる、それがSPRING VALLEY BREWERYの考えるCRAFT BEERです。
つまり醸造規模やメーカーの大小は関係なく、重要なのは醸造家のビールに対するパッション、自由な発想とそれを創造するための確かな知識や技術、そして”きちんと美味しいこと”ということになります。
また日本ビアジャーナリスト協会代表理事である藤原ヒロユキさんは、クラフトビールを『“ビールおたく”と呼ぶにふさわしい、“年がら年中ビールのことで頭がいっぱいな連中”が造りだすビール』と表現しています。
そしてそんなビールおたくが造る「伝統的なスタイルを厳守または踏襲したビール」「独自の解釈でスタイルを進化させたビール」「ユニークな副原料や醸造法を使った独創的なビール」こそが、クラフトビールに呼ぶに相応しいとも。
地ビールはクラフトビールか?
さて前述のように、日本で初めてクラフトビールを定義したのは全国地ビール醸造者協議会(JBA)ですが、JBAの公式サイトではクラフトビールのことを「クラフトビール(地ビール)」としています。この(地ビール)というのが要で、つまりクラフトビールと地ビールを同等のものとしているのです。しかし果たして「クラフトビール」=「地ビール」でしょうか?
地ビールは定義のように「地域の特産品」を使った、”お土産ビール”の域を出ないものが多いように感じます。著者はある地域の「クラフトビール」と銘打った商品を飲んだことがありますが、そのビールには特産品の「色」を表現するために着色料が使用されていました。着色料はその名の通りビールを着色するだけで味にはなんの影響もなく、つまり「あってもなくてもビールの味は変わらない」のです。そんなあってもなくても変わらないような原料を使ったビールを「クラフトビール」と呼べるかどうかと言われると甚だ疑問ですし、やはりそれは”お土産ビール”なのではないかと思うのです。もちろんお土産ビールでも美味しいビールはたくさんありますが、ただ広い目で見てそういった傾向にあるのは明らかだと思います。
ではなぜクラフトビールと地ビールを同等のものとしているかというと、日本には2010年頃からアメリカのクラフトビールが輸入され始め、その頃の日本にはまだ「クラフトビール」はありませんでした。
だけれどその輸入されたビールは大手メーカーが造るビールとは味わいが異なりなんだか個性的。そうかこのビールは、日本で言うところの「地ビール」か!よしそれでは地ビールのこともクラフトビールと呼ぼうではないか、といった感じです。(このあたりは諸説あるようです)
ちなみに地ビールの誕生は酒税法が改正された1994年。当時は地ビールブームが起き全国で200以上の小規模ブルワリーがあったそうですよ。
地ビールのほとんどは定義にあるような「地域の特産品を原料とした」ビールではありますが、クラフトビールに至ってはそれが当てはまらない商品もたくさん販売されています。JBAのクラフトビールの定義が発表されたのは2018年で、それから7年の時が過ぎた現在ではクラフトビールはますます進化を遂げていますし、多彩に変化してきています。そんなクラフトビールを7年前の”枠”に収めるのは、なかなかどうして困難ではないでしょうか?
クラフトビールと呼べるビールとは
つまりクラフトビールの定義とは、今やあってないようなものだと筆者は考えています。
だけれど忘れてはいけないのは、アメリカでクラフトビールが誕生したときのあのマインド。「伝統を重んじる心、ビールに対するパッション、自由な発想とそれらを創造するための努力、知識、技術。そして醸造家本人が本当に美味しいと思えるビールであること。」これらが全て揃ったとき、そのビールはクラフトビールと呼べるのではないでしょうか。
ではまた!
本日のまとめ
- クラフトビールの起源はアメリカで1968年ごろ
- もっと遡れば1920年~の禁酒法も関係している
- JBAの定義によるとクラフトビールとは「小規模」「大手じゃない」「伝統的か地域の特産品を使用」
- しかし近年では大手などもクラフトビール事業に参入しており、必ずしもこの定義に当てはまるとは限らない
- 地ビールとクラフトビールは別物
- 1994年の酒税法改正とともに小規模ブルワリーが増え、地ビールブームとなる。
参考文献
参考ウェブサイト
日本ビアジャーナリスト協会
「クラフトビールの定義とは?醸造規模の大小ではない。」
https://www.jbja.jp/archives/38939
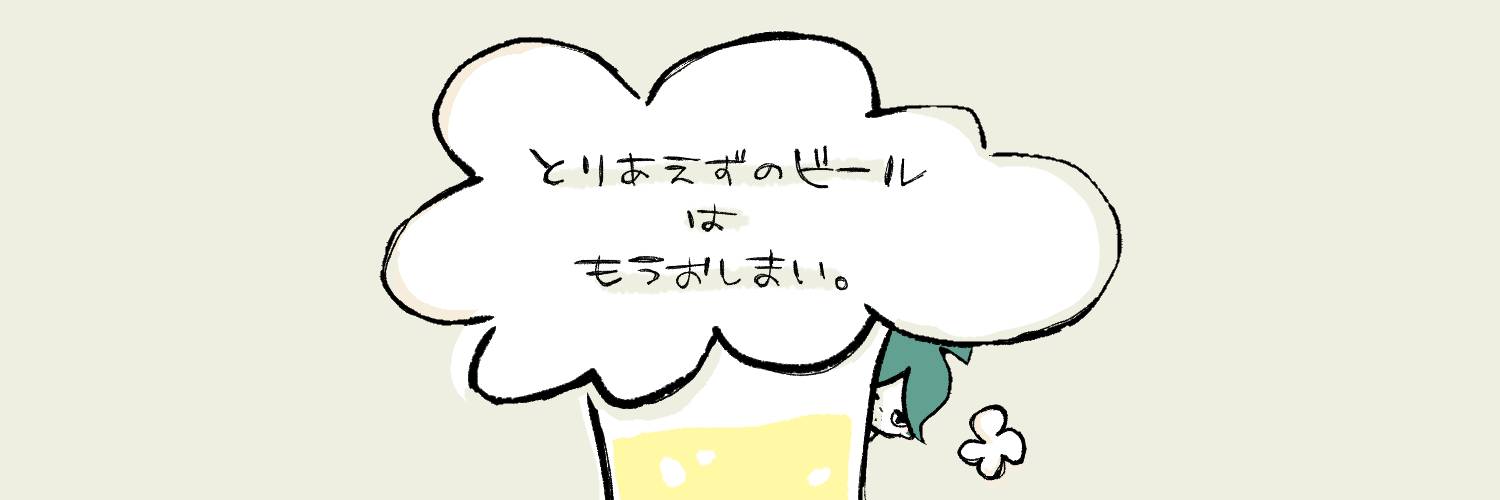
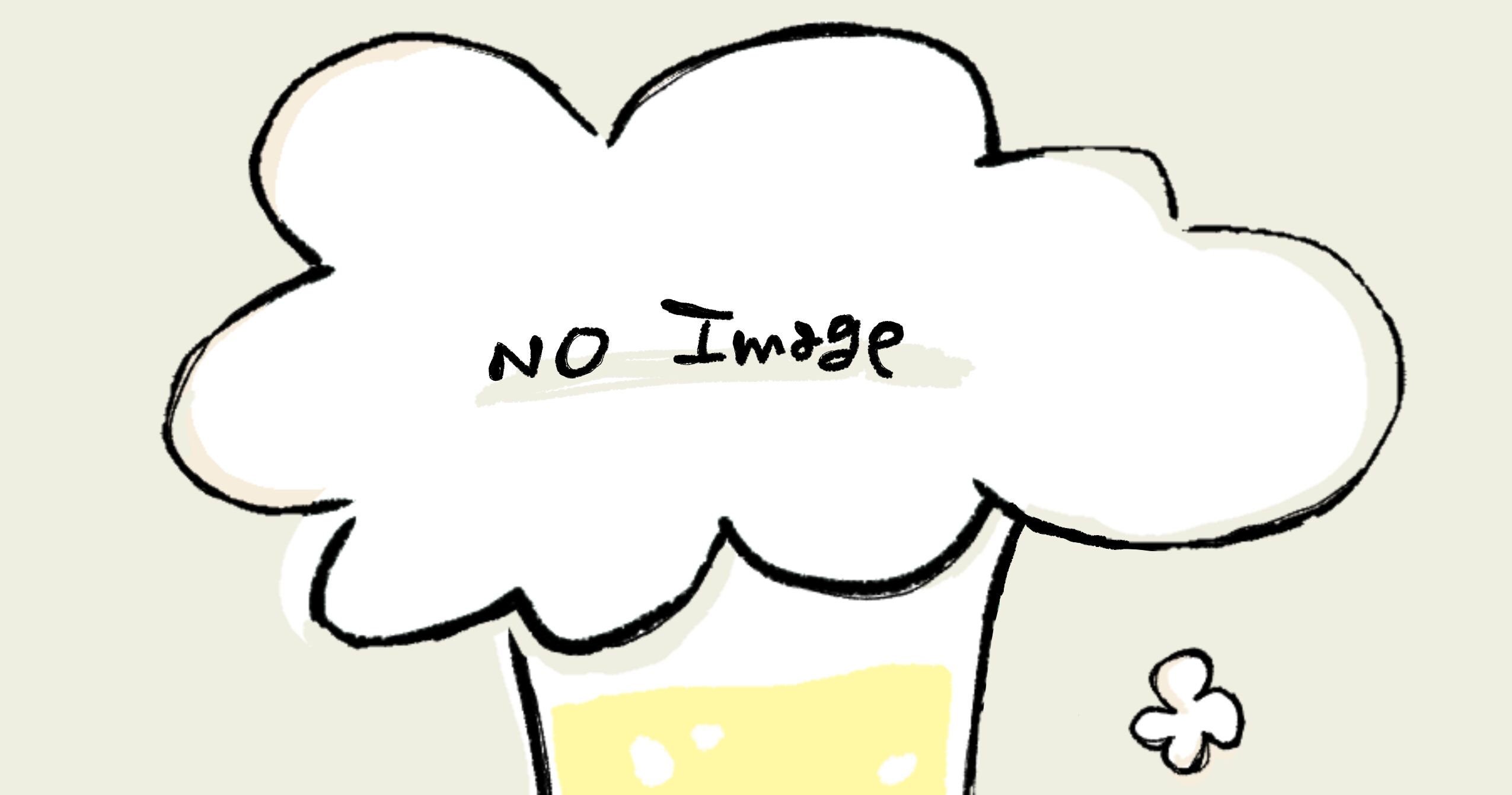




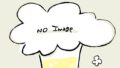
コメント