前回の【ペールエール入門編】も併せてご覧ください。
みなさん「よなよなエール」というビールをご存知ですか?これは日本のクラフトビールメーカーであるヤッホーブルーイングの看板商品のうちのひとつですが、コンビニやスーパーなのでも手軽に購入できることから、日本で最も手に入れやすいペールエールビールではないかと思います。そんなよなよなエールは【アメリカン・ペールエール】というスタイルに分類され、このアメリカン・ペールエールは今世界で大人気となっているスタイルですが実はペールエールの発祥はアメリカではありません。今回は、そんな”元祖”ペールエールのお話をしようと思います。
ペールエールの発祥はイングランド
今では身近になったペールエールですが、その発祥は18世紀イングランドの中心部「バートン・アポン・トレント」という街でした。実業家のヒュー・オルソップが1822年にティーポットの中で造ったのが始まりだなんて言われていますが、ティーポットってどういうことなんでしょうね。(笑)
とにかく、その当時のビールは全て濃色だったのに対しこのペールエールはそれよりも淡い(ペール)色をしていたためこの名前が付けられました。日本でよく飲まれるピルスナーと比べたらあまり淡色には感じませんが、ペールエール誕生前のイギリスでは濃い色のエールビールが主流でしたので、そう名付けられたのも納得です。(ちなみに今や世界のビールの7割だと言われているピルスナーの誕生は19世紀。ビールの歴史から見るとピルスナーは新参者なのです。)
決め手は水質にあり
さてでは、このバートン・アポン・トレントのエールビールは、どうして他のエールビールと比べて淡い色をしていたのでしょう?それはこの地の特殊な”水質”にありました。以前に書いた記事「ピルスナーを深く知る。」でも触れましたが、ビールにとって水質はとても重要です。一般的に、日本やチェコのプルゼニ(プルゼニはピルスナービール誕生の地です。)のような”軟水”は、ピルスナーなどの下面発酵ビール(ラガービール)に適しています。反して上面発酵ビールであるエールビールには”硬水”が最適解と言われています。なので造りたいビールによって水の硬度を調整する必要があるのですが(「水を磨く」とも言います。)、当時は水の硬度という概念なんてなかったため、それぞれの土地の水に適したスタイルのビールが造られていました。
そしてバートン・アポン・トレントの水質は察しの通り”硬水”であり、しかも相当のマグネシウムやカルシウムが含まれている超・硬水なのです。(正確には”非常な硬水”と表現するそうです。)この水の硬度を表す単位をppmといい、この数値が高いほど硬い水ということになりますが件のバートン・アポン・トレントは330mmpに対し、少し南下したロンドンは94mmpの軟水となっています。ロンドンのようにイギリスのほとんどの地域は軟水であり、これがバートン・アポン・トレントだけがペールエールを醸造することが出来た主な理由です。
水の硬度ははどのようにして決まるのか
水の硬度は、その水が雨として地上に降ってからどんな”旅”をしたかで決まります。湖や池から取った水はほとんどが軟水ですが、汲み上げられるまでに地下の岩の隙間を通ってきた地下水なら、岩の(例えば石灰岩の)カルシウムやマグネシウムをたっぷりと溶かし込んでいるのです。ここでバートン・アポン・トレントの水に話を戻しますが、このバートンの水は蒸発岩という主成分が石膏の岩の隙間を通っているため、マグネシウムやカルシウムがたくさん溶け込んだ超・硬水となり、また石膏由来の”硫黄の香り”が付与されているのです。この水で造られたビールは一瞬鼻先に硫黄臭を感じるそうで、「バートン・スニッチ」と呼ばれています。当時はなぜバートンのビールだけにこのような現象が起こるのかがわからず、他の醸造所がバートンのペールエールを真似しようと努力しても成功することはありませんでした。けれど次第にその原因が「石膏」にあると気付き始め、軟水に石膏を加えて水の硬度を高め硫黄分を調整する技術を開発したのです。このような石膏による水の硬度調整をバートンの名から「バートン化」と呼ぶようになりますが、現在ではただ単に軟水を硬水に調整することをバートン化と呼ぶのが一般的です。このバートン化技術が確立されると、ペールエールというスタイルが瞬く間に世界に広がることになるのです。
日本にも輸入された「バス・ペールエール」
イギリス発祥のペールエールを【イングリッシュ・ペールエール】と呼びますが、しっかりとした麦芽のコクとイギリス産ホップ由来の花やハーブ、紅茶のような香りが特徴です。しかしながら現在日本でイングリッシュ・ペールエールをお目にかかれる機会は少なく、手に入れやすいのはRISE & WIN Brewaryの「カミカツペールエール」か、HARVEST MOON Brewaryの「ペールエール」あたりかと思います。あとは英国風パブ「HUB」の「ハブ・エール」もイングリッシュペールエールなので、機会があれば是非飲みに行ってみて下さい。(他にも日本で飲めるイングリッシュペールエールがあったら教えてください!)
さてそんな希少なイングリッシュ・ペールエールですが、日本に初めて輸入されたビールはバートン・アポン・トレント産のペールエールだったと言われています。幕末に「オールソップ社」と「バス社」の2社から輸入され、特に人気だったのが「バス社」のペールエールで赤い三角形がトレードマークです。この赤い三角形はバス社の商標(英国の登録商標第1号!)でもあり、当時開港場の近辺ではいたるところでこのマークが見られたといいます。そして明治(1686年)に入ってもバス社のペールエールの人気は衰えず、偽造品まで出回り1871年には東京府が偽造を禁止する府令を出したほどでした。ちなみに日本でビールが醸造され始めるのは1870年ですので、それまで日本で飲まれていたビールは全て輸入品の、しかもエールビールということになります。(なのになぜ現在の日本のビールはピルスナーばかりなのかはまた別の機会に。)
このバス社のペールエール(バス・ペールエールとも呼ばれます。)はヨーロッパ大陸にも輸出されており、たくさんのファンを獲得しました。フランス画家の巨匠エドゥアール・マネの作品「フォリーベルジェールのバー」にも描かれていますので、是非探してみてくださいね。
今や世界中で飲まれているペールエールビールですが、このような歴史があったのは驚きですよね。ビアスタイルは現在150種類を超えると言われていますが、すべてのスタイルにはそれぞれの歴史があるのです。それはまた別の機会にご紹介出来たらと思います。
ではまた!
カミカツペールエールのオンラインストアはこちら!

ふるさと納税もあります♬
参考文献
参考WEBサイト
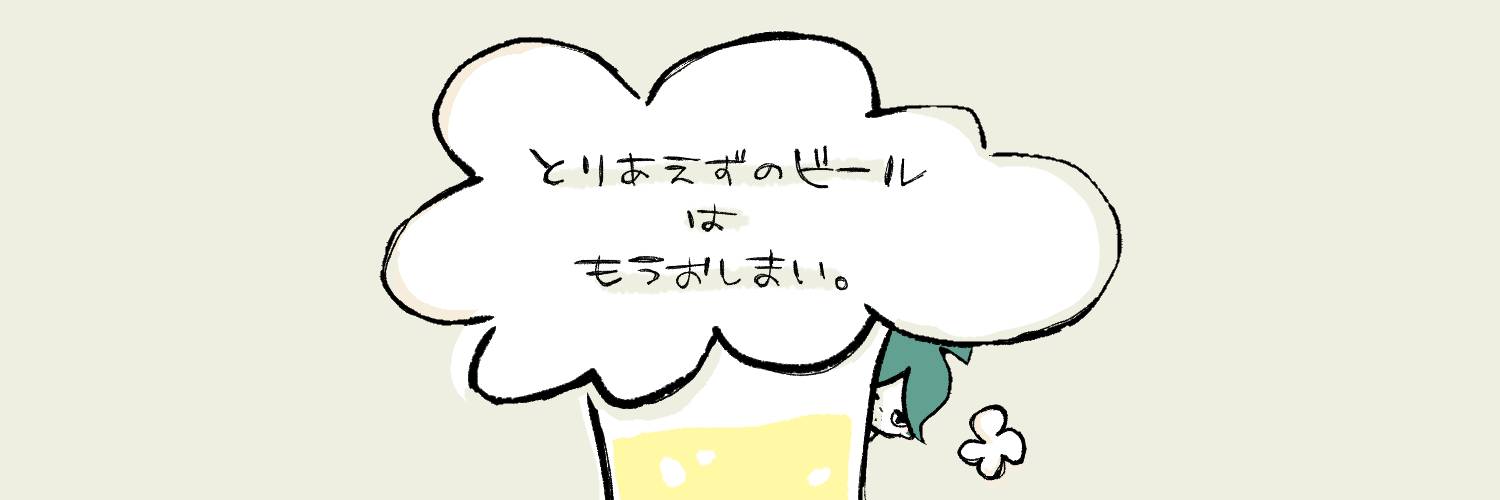






コメント