はじめに
ビールは「麦酒」と書くように麦で造られるお酒ですが、ビールを造る上でなくてはならないのが「ホップ」です。日本の酒税法やドイツのビール純粋令でも、ビール醸造においてホップの使用を不可欠としています。ホップとは一体何者なのか、何のために使用されるのか、そしていつ頃登場しビール造りに使われ始めたのか…今回はそんな「ビールの魂」とも呼ばれる、ホップについてのお話です。

日本の酒税法では、ビールは「アルコール分が20度未満で、麦芽、ホップ、水などを原料として発酵させたもの(麦芽比率50%以上)」と定められています。
ホップとは?

ホップはアサ科に属する雌雄異株の、多年生のつる植物です。春に芽を出し、花が咲き始める初夏には7mもの高さにまでつるを伸ばします。「雌雄(しゆう)異株」というのはその名の通りオスとメスが株によって分かれている植物のことで、ビールの醸造に使われるのはメス株にあるわずか数センチの花の部分のみです。
そしてこの花の部分を「球花」といい、球花の中心部にある「ルプリン」という器官によってビール特有の苦味や香りがもたらされるのです。
ホップの役割
先にも書いたように、ホップにはビールに苦味や香りを与える器官が備わっていますが、その他にもたくさんの役割があります。ここではそれぞれを見ていきましょう。
1、苦味を付ける
ルプリンに含まれるα酸という成分は煮沸されることによりイソα酸に変わり、これが苦味の元となります。主に麦汁(ばくじゅう/ビールの素となる液体)の煮沸開始時にホップを投入し、麦汁と一緒に煮沸されます。これを「ケトルホッピング」といいます。
クラフトビールの缶や瓶などにはまれに「IBU」という国際苦味単位が表記されていることがありますが、この数値が高いほど苦いビールとされピルスナーなどは20程度、苦味を特徴とするIPAは40を超えます。

麦芽をお湯で煮るとお粥状のものができ、それをろ過したものが「麦汁」です。麦汁を煮沸する理由には殺菌やタンパク質の凝固、糖度調整などがあります。
2、香りを付ける
ルプリンに含まれる香気成分が麦汁に溶け出すことで香りを抽出することができます。この香気成分は煮沸するとほとんど気化してしまうので、ホップ投入のタイミングは麦汁煮沸終了間際か、煮沸した麦汁が完全に冷めてからです。煮沸終了間際に投入することを「レイトホッピング」、煮沸終了後に投入することを「ドライホッピング」といいます。

ペールエールやIPA(インディア・ペールエール)など、ホップの香りが強烈なビールは主にドライホッピングによって香り付けをしています。
3、泡立ちを良くする
泡はビールにとって重要な存在ですが、ホップをたくさん使ったビールほど泡立ちが良くなると言われています。

4、殺菌効果を高める
ホップには殺菌効果があることが認められています。18世紀頃にはイギリスからインドへとビールを輸送するためにホップを大量に使用し、無事腐らずに長い航海に耐えうるビールを造り出しました。このビールがIPAの起源です。別の記事で詳しく解説しています。
ホップの分類
ホップには香り付けが得意な品種、苦味付けが得意な品種、その両方を兼ね備えている品種に分類することができ、それぞれ「アロマホップ」「ビターホップ」「デュアルホップ」といいます。
先にも述べたようにビールの苦味はルプリンのα酸が煮沸によりイソα酸に変わることでもたらされますが、このα酸の含有量はホップの品種によって様々で、α酸が高ければ高いほど煮沸により苦いビールが造り出せるということになります。

ビターホップの代表品種である【マグナム】のα酸は11.0〜16.0%、ピルスナーなどに使用される【ザーツ】は2.5〜4.5%です。
またアロマホップは「ファインアロマホップ」と「アロマホップ」に分類され、ファインアロマホップはアロマホップに比べて香りや苦みが穏やかで、上品な品種とされています。ファインアロマホップはヨーロッパの伝統的な品種でその数は少なく、代表的なものに【ザーツ】や【ハラタウ・ミッテルフリュー】など、があります。
ホップの加工
収穫されたホップは乾燥させ粉砕、そして圧縮しペレット状に加工して使用されます。このペレットホップが使われ始めたのはつい最近20世紀後半のことで、それ以前は乾燥後プレスされたものが常用されていました。しかしホップを輸送する際にかさばることや保存中に成分を損なってしまうことから、現在ではペレットホップが主流となっています。
(☟がペレット状のホップ。実はネットでも簡単に手に入ります…すごい時代になったものですね。)

ホップの収穫は8月中旬から9月上旬。この時期になるとペレットではなく生のホップ(フレッシュホップ)を使用したビールを販売するブルワリーが続々と出てきますよ!お楽しみに♬
ホップ起源
ホップは7、8世紀頃ヨーロッパで栽培されていたという記録が残っていますが、その頃はただの観賞用だったようでビール醸造には使われていませんでした。
では実際にビール醸造にホップが使われ始めたのはいつ頃かというと、確かな記録があるのは12世紀のドイツです。とある女子修道院の院長がビールの味付けにホップを添加していたという記録が残っていますが、常用されるようになったのは14世紀頃といわれています。
古来から修道院ではビール造りが盛んに行われており、巡礼者などに振る舞ったとされています。その文化は現在も残っていて、修道院で造られたビールは「トラピストビール」や「アビィビール」と呼ばれ実際に買うこともできますよ!その味わいは修道院によって全く違うので、色々飲み比べてみるのも楽しいです。

トラピストビールはトラピスト会修道院のみで造られるビールで、世界にわずか11ヶ所のみ!(2025年現在)
アビィビールはトラピスト会以外の修道院が関与したり、かつて修道院で行われていた醸造方法やレシピを一般の醸造所に委託して造られるビールを指します。
ホップが登場するまでのビール
世界最古のビールは「シカル」と呼ばれ、5000年以上前のメソポタミア時代に誕生したと言われています。現在のホップに相当する香味付け、腐敗防止には薬草、ナツメヤシなどの果実、スパイス、木の皮、蟹の爪(!)などなど、様々なものを組み合わせて使われていたそうです。
その後紀元前18世紀頃(3000年前くらい)からヨーロッパに住み始めたゲルマン民族達もビールを醸造していた記録が残っており、こちらはヤチヤナギなどのハーブを使用していました。

シカルは香味付け材料の組み合わせによってその味わいは無限大!サソリに刺されたときに飲む「薬草入り毒消しビール」なんてのもあったそう。
時は進み中世ヨーロッパでも、薬草などを独自にブレンドした「グルート」と呼ばれるものが使われていました。グルートの材料はヤチヤナギ、アニス、フェンネル、コリアンダー、セイヨウノコギリソウなどとされていますが、その配合と製造は門外不出だったため記録はほとんど残っていません。

グルートの製造は修道院や都市などが独占していて、ビール醸造業者に販売して利益を得ていました。これを「グルート権」といいます。
ホップビールの登場
ドイツの第二の都市であるハンブルグでは14〜15世紀からビールの輸出が盛んに行われ、この頃からようやくビール醸造にホップが使われ始めました。グルート権で巨額の利益を得ていた都市などはこれをなんとか抑え込もうとしましたが、抗菌作用・香味付けともにグルートがホップに勝るわけもなく、グルートを使ったビールは徐々に衰退していったのです。
またイギリスにも15世紀にホップを使ったビールが輸入され、当時はグルートを使ったビールを「エール」、ホップを使ったビールを「ビール」と呼んで区別していました。慣れ親しんだグルートビールを好む声が多かったのとグルート利権により、イギリスでホップが普及するのは17世紀以降となります。

イギリスのグルートにはキヅタなどが使われ、ホップビールに比べると非常に味が濃かったそうです。
おわりに
いかがだったでしょうか?ビールの歴史が5000年と考えると、ホップが使われ始めたのがつい最近のように感じますね。グルートを使ったビール…ぜひ飲んでみたいものです。
ちなみにキリンビールがグルートビールの再現を試みていて、その記事がなかなか興味深いです。気になった方は覗いてみてください。
おまけ(ホップ雑学)
・ビール350ml缶1本にホップの球花が5個必要
・12世紀ホップビールは悪しきものとされ、「ホップは人の内の憂鬱を育て魂を惨めにし内臓に重荷を背負わせる」と訴える修道院があった(グルート利権?)
・しかしホップ自体は万病に効くとされ、安眠のため枕の詰め物にも
・ヒトが判断できる苦味レベルはIBU150が限界(もしくはそれ以下)
・世界にはIBU2000を超えるビールがある
・ビールは貯蔵しすぎるとIBUが下がる
日本でも買えるトラピストビール

シメイ(Chimay)
ベルギーのスクールモン修道院で造られているトラピストビール。トラピストビールの中で最初に市販されたのがこのシメイといわれています。
シメイのビールは「シメイブルー」「シメイホワイト」「シメイレッド」などいくつも種類がありますが(戦隊ヒーローみたいだ!)、なかでも筆者のお気に入りは「ブルー」です。写真でも分かるように泡立ちが非常によく、瓶内二次発酵・長期熟成しているのでアルコール度数高め、味濃いめ、そして複雑な香りです。ちょっとワインみたい。でもしっかり麦芽を感じることができ、後味はカラメル。深夜にちびちびやりたいやつです!成城石井とかビールに強い酒屋さんには置いてあるイメージです。見つけたらぜひゲットしてみてください。
楽天でも「ブルー」「レッド」「ホワイト」の人気カラー飲み比べセットが買えます。しかもシメイ専用グラス付き!「シメイを飲むために開発された、この専用グラスで飲むと、驚くほどに味わいが違い、ビールの概念が変わります。」だそうで。著者も欲しいぞ…!
ではまた!
参考文献
記事を書くときの筆者の必需品!サイエンスな話が多いので読むのに苦労しますが、ホップやら麦芽やら酵母やら、ビールに関する専門的な知識が詰まっています。
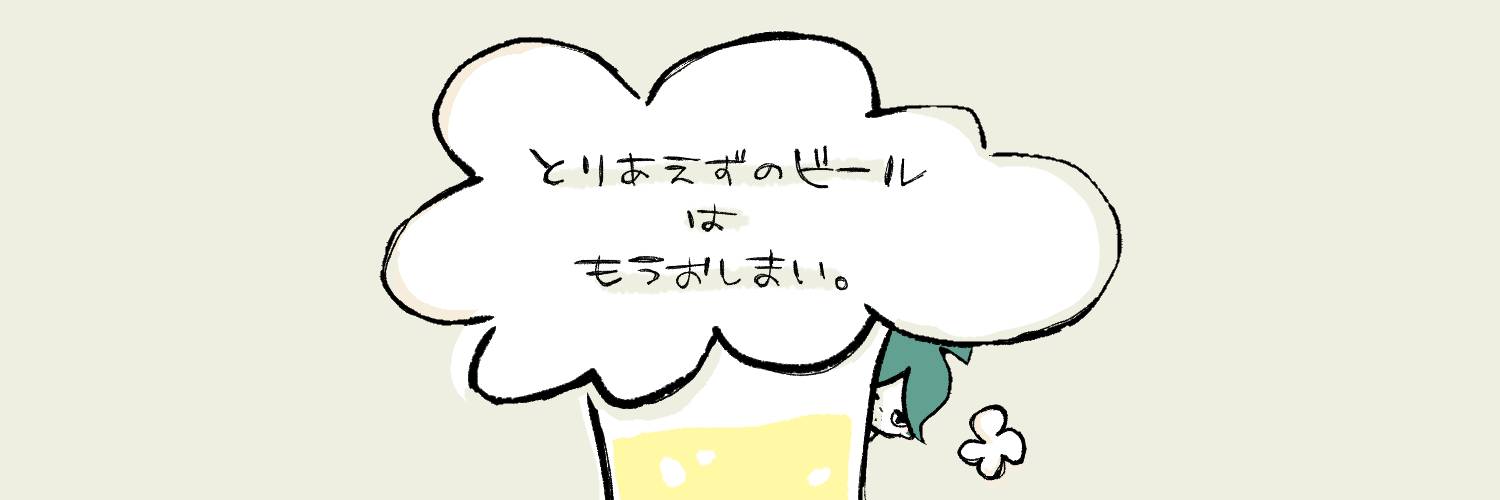





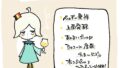
コメント